スギ〈杉〉(スギ科 スギ属) 花期は2〜4月。
日本特産で各地に広く自生し、また有用樹種として最も多く植林されている。
大きいものは高さ50mにもなる常緑高木。雌雄同株。
葉は長さ約1cmの鎌状針形。
雄花は前年枝の先に多数つき、淡黄色で長さ5〜8mmの楕円形。
雌花は前年枝の先に1個つき、緑色で球状。
球果は長さ2〜3cmの卵状球形で10月ごろ成熟する。
【今年はスギの雄花が非常に多く目につきます】
09.2.15 撮影
【上の画像を拡大しました】
09.2.15 撮影
「雄花は前年枝の先に多数つき、淡黄色で長さ5〜8mmの楕円形」
【花粉が多く出ていた雄花の一つを“ファーブルフォト”で撮ってみました】
09.2.17 撮影
「花粉は風媒花の中でも特に小さくて軽く、風に乗って遠くまで運ばれる」
「茶色に黄色い縁取り」は、割れ目で、中にびっしり黄色い花粉が見えましたが、
割れ目の奥にピントを合わせにくくて、分かりにくい画像になってしまいました。
【雄花が花盛りの今、雌花は】
09.2.17 撮影
「雌花は前年枝の先に1個つき、緑色で球状」
【雌花を正面から】
09.2.1 7撮影
この段階の全体の直径は5mmほどです。
【上の画像を拡大しました】
09.2.15 撮影
上の、雌花を横から撮った状態と同様の画像を図鑑では「開花直前」とありますから、
これは「開花直前の雌花」でしょうか。
きょうは昼前に秋吉台に向かいましたが、途中から雨に。
カメラは車の中に置いたまま、ゆっくりと林道を往復、木や草、シダを見て歩きました。
実はこの私、「スギ花粉症」と名前が知られる前の、今から35年前からの「元祖」で、春先に毎年、熱がでない鼻風邪状態がひどくて、医者に行って薬をもらっても飲むのをやめるとひどい症状がでて、薬を長い間飲み続けながら、医者が首を傾げてレントゲンを撮ったり・・・。
結局、分からないまま、季節が来ると同じことを繰り返していました。
花粉が原因とは知らないものだから、晴天の日には「ばい菌を殺せ!」と、お布団を干して、わざわざ花粉まみれで寝てたものだから、ティッシュを一晩中使い、両鼻がつまって息を口でするため、食べ物が飲み込めないので、げっそりとやつれていました。
発症して5年後くらい(今から30年くらい前)に「スギ花粉症」と知られるようになり、抗ヒスタミン剤での対症療法でしのいで、ここ10年ほどは、花粉が飛び始める前に2週間以上服用していると効果があるという「抗アレルギー剤」を、1月半ばから飲んでいます。
抗ヒスタミン剤は全く飲まず、目薬だけでしのげるようになりました。
秋吉台を歩き始めた頃は、スギの雄花を指ではじいて、クシャン!と言ったら「スギが開花」でしたが、現在ではその手は使えなくて、花粉を「目視」して、開花としています。
時の流れを感じますね。
※ 日記の花期は、私が秋吉台で調べてきたものを使用しています。
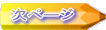
 |