シロツメクサ〈白詰草/別名クローバー〉(マメ科 シャジクソウ属) 花期は4〜12月。
江戸時代にオランダからガラス器を送ってきた時、
壊れないように乾燥したシロツメクサを詰めたことから詰草の名が生まれた。
ヨーロッパ原産の多年草で牧草として世界中に広がった。
茎は地をはって長く伸びる。
葉は3小葉、ときに4小葉からなり、葉柄は5〜15cmと長い。
小葉は長さ1〜1.5cmの広倒卵形で、表面に斑紋があるものが多い。
花は白色で長さ約1cm、多数集まって球状の花序をつくる。
【①を拡大しました - 小さな蝶形花が30〜70個集まって花序をつくっています】
12.5.4 撮影
【②ピンクのシロツメクサを見つけました - 家族旅行村で】
12.5.11 撮影
【③】
12.5.11 撮影
【③を拡大しました - 花には短い柄があり、受粉した花は下向きになる】
12.5.11 撮影
この色の花でタチオランダゲンゲというのがありますが、
「タチオランダゲンゲの萼裂片は、萼筒と同長か少し長い」ので、残念、シロツメクサでした。
(日記を中断して、今の様子を見てきましたが、もう花は無く、葉だけでした。)
* * * * * * *
【④ドリーネ耕作から帰水に向かう途中にあった雑木林が完全に無くなりました
- ききようが原から】
12.11.29 撮影
所有者の承諾を得て、伐採手続きをされて・・・。
【⑤配川さんお一人のご尽力で、200本あったスギも全て伐採 - すぐ上のの遊歩道から】
12.11.29 撮影
【⑥配川さん、お疲れさまでした - 1人日当15000円かかるため、お一人で伐採されたそうです】
12.11.29 撮影
来年の山焼きで、燃えてくれるといいですね。
|
※ 日記の花期は、私が秋吉台で調べてきたものを使用しています。
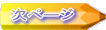
 |