オケラ〈朮〉(キク科 オケラ属) 花期は9〜10月。
古名のウケラがなまったもので、語源ははっきりしていない。
やや乾いた草地に生える高さ30〜100cmの多年草。雌雄異株。
葉は長い柄があり、3〜5裂し、裂片のふちには刺状の鋸歯がある。
頭花は白色またはやや紅色を帯び、直径1.5〜2cm。
総苞の周囲に魚の骨のような苞がある。
【①を拡大しました - 頭花には多数の小花がある】
12.10.5 撮影
【② - ①の3週間経った、今の頭花】
12.10.26 撮影
【②を拡大しました - 咲いて時間が経った雄花ですね】
12.10.26 撮影
「雄花では花柱の先がふくれ、短く2裂し、裂片は正三角形。雄しべは花粉ができる」
【③咲いたばかりの雄花と思われます - 】
12.10.7 撮影
【④雌花】
12.10.26 撮影
【④を拡大しました】
12.10.26 撮影
【⑤ - ④に近寄って撮りました】
12.10.26 撮影
「雌花では花柱の先がわずかにふくれ、短く2裂し、
裂片は3角形で反り返る。雄しべの葯に花粉ができない」
|
昨年冬、時間が取れるようになって、枯れたオケラの花のあとを見て回っても雄花か雌花か見極められませんでした。
このたび、門田先生に、アザミの両性花と雌花を教えていただき、分からないままにしていたキク科の頭花はきっちりと撮れば何とかなると思うようになり、オケラを1株1株見て回った結果、雌花・雄花がほぼ同じくらいの数あることが分かりました。
※ 日記の花期は、私が秋吉台で調べてきたものを使用しています。
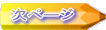
 |