マタタビ〈木天蓼〉(マタタビ科 マタタビ属) 花期は6〜7月。
山地に生える落葉つる性木本。雌雄異株。
つるはほかの木や岩などにからみついて長く伸びる。葉は互生。
広卵形で先は鋭くがり、基部は円形〜切形、ふちには刺状の小さな鋸歯がある。
枝の上部につく葉は花期に表面が白色になる。
本年枝の中部付近の葉腋に芳香のある白い花を下向きにつける。
花は直径2〜2.5cm。花弁は5個。雄しべは多数、葯は黄色。
両性花の花柱は線形で多数あり、放射状に開出する。萼片は5個。
【②雄株】
12.6.25 撮影
【②を拡大しました】
12.6.25 撮影
【②を拡大しました】
12.6.25 撮影
【③雌株】
12.6.25 撮影
【③を拡大しました】
12.6.25 撮影
【④ − 今年は開花前から見てきましたが、両性花のきれいな姿が見られません】
12.6.25 撮影
|
ここで6月21日、離れた場所から撮った画像によって、オオハンゲを開花確認しました。
きょうは頑張って近づいて撮るつもりで来たところ、急斜面の崖から落ちた大きな岩が3個転がっています。オオハンゲの場所から30mくらいの所ですが、まだ崖の途中で止まっている岩も見えます。
「どうしよう」。勇気が出なくてオオハンゲを諦め、マタタビの雄花を撮っていたら、一瞬大きな音が聞こえました。
この場所に十数年来ていますが、岩が落ちたのを見たのは初めてです。
(秋吉台科学博物館には連絡済みです。)
※ 日記の花期は、私が秋吉台で調べてきたものを使用しています。
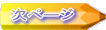
 |