ヒノキ〈檜〉(ヒノキ科 ヒノキ属) 花期は3〜4月。
山地に生える高さ30mになる常緑高木。雌雄同株。葉は十字対生。長さ1〜3㎜の鱗片状で、先端はとがらない。花は枝先につき、雄花は長さ2〜3㎜の楕円形で赤みを帯び、雌花は長さ3〜5㎜の球形。球果はは直径約1㎝の球形。その年の10〜11月に熟し、赤褐色になる。
昔、この木をすりあわせて火をおこしたので、「火の木」からつけられた名前だそうです。
材は日本の針葉樹の中で最も評価が高く、ヒノキ林の多くは植林されたもので、秋吉台でも植林があちこちで見られます。
遠くからでは1年中同じように見えるヒノキを整理してみました。
【球果を】
06.1.21 撮影
「熟すと果鱗が開いて種子を出す。果鱗の先は厚く楯状に発達し、普通8〜10個ある。
果鱗には種子が2〜4個ずつつく」
果鱗と果鱗の間に、残っている種子が見えます。
【こんなのも―種子を出したあとの球果】
06.1.21 撮影
【こんな時もありました―裂開前の球果】
05.11.10 撮影
【こんな時も―雄花】
05.4.11 撮影
「雄花は長さ2〜3mmの楕円形で、赤みを帯びる」
【雌花を探しました】
05.3.29 撮影
「雌花は長さ3〜5mmの球形」
ですが、目立つ雄花にピントが合った画像ばかりでした。(反省)
※ 日記にある花期は、私が秋吉台で調べてきたものです。
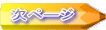
 |

