ヒマラヤトキワサンザシ〈別名カザンデマリ〉(バラ科 トキワサンザシ属)
花期は5〜6月。
ヒマラヤ原産で日本には昭和初期に渡来した常緑低木。
高さ2mほどになり、よく枝分かれする。
葉は互生。長さ2〜5cmの長楕円形または披針形で革質。
両面とも無毛で、ふちには細かい鋸歯がある。
短い枝の先に散房花序を出し、直径約1cmの白い花を多数開く。
果実は直径7〜8mmの球形で、光沢のある鮮紅色または橙赤色に熟す。
【上の画像を拡大しました】
11.6.6 撮影
【短い枝の先に散房花序を出し】
11.6.6 撮影
「直径約1cmの白い花を多数開く」
【上の画像を拡大しました】
11.6.6 撮影
4月から、希少種と帰化植物の個体数を調べる植物調査を頑張っています。
私の班は4人、毎週木曜日を調査日と決めていますが、真面目で(?)気心が知れた人ばかりなので、相談しながら、できる人とはもう1日、受け持ちの地域を歩き回っています。
班の割り当て以外に、私は林道や駐車場の帰化植物の調査をやるのですが、草刈りとの戦いで、 雨の日にも傘差して、ひたすらグルグルと駐車場を歩き回っています。
そんな中で目に入ったヒマラヤトキワサンザシの花です。きれいに撮れたと思っています。
精一杯頑張ってきた日々を抜け出したからか、このところ随分ゆとりができた感じで、それが画像にも写っているのではないかな。そうであって欲しいな、と。
※ 日記の花期は、私が秋吉台で調べてきたものを使用しています。
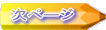
 |